| 1. |
「島根県出雲市平田方言の疑問文における「ダ」:「行くダカ」は「行くのか」と同じか」
野間純平
方言の研究
No.:11
219-243頁
その他
2025年
10月
|
| 2. |
「島根県出雲市平田方言におけるとりたて否定形」
野間純平
山陰研究
No.:17
91-107頁
大学・研究所等紀要
2025年
3月
|
| 3. |
「地域言語・方言—特集 2022年・2023年における日本語学界の展望(1)」
野間 純平
日本語の研究 = Studies in the Japanese language / 日本語学会 編
vol.:20
No.:2
85-92頁
学術雑誌
2024年
8月
ISSN:13495119
|
| 4. |
「現代日本語における準体助詞「ノ」と「ン」 : 撥音化に関わる文法的条件—これからの現代語文法 令和四年五月特集号」
野間 純平
国語と国文学
vol.:99
No.:5
全:13頁
98-110頁
学術雑誌
2022年
5月
ISSN:03873110
|
| 5. |
「島根県出雲市平田」
野間純平, 友定賢治
日本の消滅危機言語・方言の文法記述
215-266頁
大学・研究所等紀要
2022年
3月
|
| 6. |
「鳥取方言における場所を表す助詞「カラ」」
長谷早紀, 野間純平
山陰研究
No.:14
85-99頁
大学・研究所等紀要
2021年
12月
|
| 7. |
「2019年度島根大学隠岐方言調査」
野間純平
隠岐の文化財
No.:37
全:10頁
33-42頁
大学・研究所等紀要
2020年
3月
キーワード:隠岐方言 フィールドワーク
|
| 8. |
「大阪方言の平叙文における「ネンナ」―「ネン」に固有の意味特徴―」
野間純平
阪大社会言語学研究ノート
No.:16
全:20頁
35-54頁
大学・研究所等紀要
2019年
7月
キーワード:大阪方言 ノダ ネン ンヤ
|
| 9. |
「2018年度島根大学隠岐方言調査」
野間純平
隠岐の文化財
No.:36
全:10頁
20-29頁
大学・研究所等紀要
2019年
3月
|
| 10. |
「2017年度島根大学隠岐方言調査」
野間純平
隠岐の文化財
No.:35
全:12頁
1-12頁
大学・研究所等紀要
2018年
3月
|
| 11. |
「大阪府八尾市方言の素材待遇形式ヤルの機能―三者の関係を表すマーカー―」
酒井雅史・野間純平
日本語の研究
vol.:14
No.:1
全:17頁
1-17頁
学術雑誌
2018年
1月
ISSN:13495119
キーワード:待遇表現 素材待遇形式 ヤル 大阪府八尾市方言 〈ウチ〉マーカー
|
| 12. |
「宮津市方言の原因・理由表現「デ」「サカイ」―談話データにもとづく使い分けの実態―」
野間 純平
阪大社会言語学研究ノート
No.:15
全:14頁
22-35頁
大学・研究所等紀要
2017年
11月
キーワード:宮津市方言 原因・理由表現 談話 デ サカイ
|
| 13. |
「鹿児島県甑島里方言の終助詞」
白岩広行・門屋飛央・野間純平・松丸真大
阪大日本語研究
No.:29
全:29頁
187-215頁
大学・研究所等紀要
2017年
2月
ISSN:09162135
キーワード:終助詞、間投助詞、相互承接、平叙文、疑問文
|
| 1. |
昔話資料のデータベース整備を続けている。このプロジェクトでは、県内各地で録音された古い民話のテープを電子化し、方言研究に利用できるよう整備する。このデータベースが完成すれば、地域の方言を記録・保存に大きく貢献できるものと思われる。 |
| 2. |
出雲地区、なかでも出雲市平田での方言調査を継続して行っている。前年度に口頭発表した内容は論文化して査読つき雑誌に投稿し、掲載が決定した。 |
| 3. |
新たな科研プロジェクトとして、昔話資料のデータベース整備を開始した。このプロジェクトでは、県内各地で録音された古い民話のテープを電子化し、方言研究に利用できるよう整備する。このデータベースが完成すれば、地域の方言を記録・保存に大きく貢献できるものと思われる。 |
| 4. |
出雲地区、なかでも出雲市平田での方言調査を継続して行っている。本年度の研究業績はその調査の成果によるものである。 |
| 5. |
出雲地区、なかでも出雲市平田での方言調査を継続して行っている。調査の成果は、個人の研究や、参加している科研費プロジェクトに生かされている。 |
| 6. |
感染対策を講じつつ調査継続が可能な出雲市において、方言調査を引き続き行った。その成果として、出雲市平田方言の文法概説(論文)を発表することができた。この論文は、これまでの出雲方言調査の集大成となるものであり、今後の研究の出発点となるものでもある。 |
| 7. |
新型コロナウイルスの影響で、毎年行っている隠岐の島町での方言調査が行えなかったため、隠岐の島町教育委員会の協力のもと、オンライン調査を行った。 |
| 8. |
前年度までと同様に、山陰地域をフィールドとした方言調査を行った。主に出雲・隠岐地区において、消滅の危機に瀕した伝統方言の記述を目的とした聞き取り調査である。また、石見地区における方言会話の文字化作業も積極的に行い、研究データが少ない地域のデータ整備を急いだ。 |
| 9. |
国立国語研究所共同研究プロジェクト研究員として、出雲および隠岐地域の方言調査を行った。その成果の一部は、国立国語研究所にて行われた研究発表会にて発表した。
また、島根県だけでなく、鳥取県倉吉市においても方言調査を行った。その成果は報告書『方言文法辞典資料集(4)』に「活用体系記述」として掲載された。 |
| 10. |
前年度に引き続き、山陰地域をフィールドとした方言の調査研究を行った。消滅の危機に瀕した伝統方言の記録・保存を目的とした研究だが、本年度は記録・保存だけでなく継承に関する活動も行った。まつえ市民大学サポーターの会主催の「出雲弁シンポジウム」では、研究成果の発表だけでなく、出雲方言の継承に関する話題提供を行った。また、隠岐の島町立の中学校において、ふるさと教育の一環としての「方言の授業」に参加した。 |
| 11. |
国立国語研究所共同研究プロジェクト研究員として、出雲地域の方言調査を行った。このプロジェクトは5年間かけて行う予定であり、その初年度である本年度においては、一定の成果を得ることができた。 |
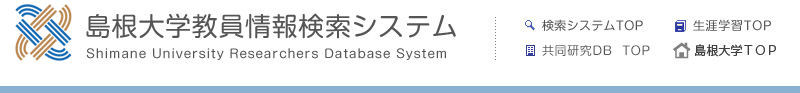

 学部等/職名
学部等/職名 書籍等出版物(著書)
書籍等出版物(著書) 論文(論文等)
論文(論文等) MISC(報告書等)
MISC(報告書等) 講演・口頭発表等(学会発表)
講演・口頭発表等(学会発表) 委員会・学会役員等
委員会・学会役員等 島根県を中心とした山陰地域に貢献する研究活動の改善の取組み
島根県を中心とした山陰地域に貢献する研究活動の改善の取組み